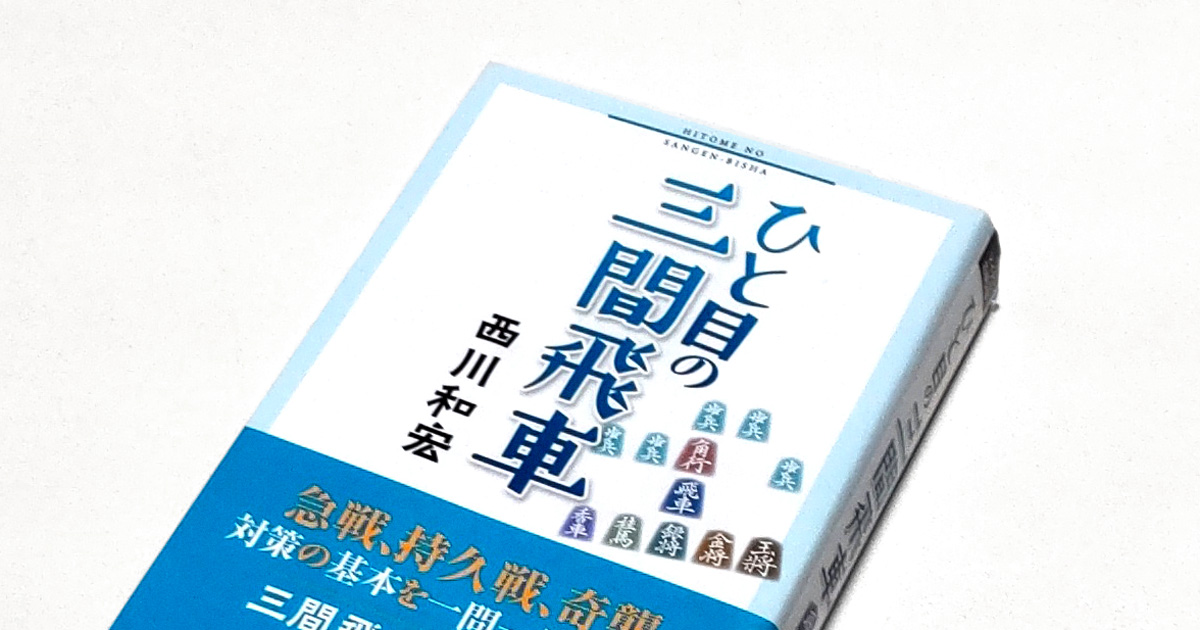2025年5月に読んでいる将棋の本は、西川和宏『ひと目の三間飛車』(マイナビ出版 、2024年)です。
私は居飛車で戦いますが、なぜか三間飛車の本。
本書を手に取った理由のひとつは、本の装丁が、おしゃれで素敵な色づかいだからです。昭和ぽっかたり、ごつごつしたりの装丁の将棋本は最近減っていますが、ここまでさわやかにデザインを振ってくるとは、文字通りの一目で心ひかれてしまいました。
振り飛車の思考が知りたくて、振り飛車の将棋本を時々のぞいていますが、ついに三間飛車まで手を広げてしまいました。飛車の上に、角がいる。その上に歩もある。飛車先が二重に止まっている三間飛車という構えは、不思議でなりません。それがどんな世界か、前々から興味があったというのが、もうひとつの手に取った理由です。
さて本書は、急戦編・持久戦編・その他の戦型編と大きく3つに分かれます。初手から一手ずつポイントとなる局面での問題と解答を掲載しています。
まえがきに「特に重要な考え方については繰り返し現れるようになっている」とありますが、その通りの解説となっています。居飛車を指す私でも、なにが三間飛車の基本中の基本なのか、なにを狙って駒を動かすべきか、形勢が分かれる局面でどう指すべきか等が、とても分かりやすかったです。
また同じく、まえがきに「三間飛車の真髄は『さばき』です。「さばき」の感覚を身につけるつもりで、問題を解き進めてください。」とあります。
私は、歩一枚や小駒も大事にして、なにが何でも駒損を避ける。それがために大局的に劣勢になってしまう、という傾向があるように思っています。自分でもよくないクセだなと思いつつ、なかなか直りません。
三間飛車はその特有の構えもあって、角も飛車も銀も、自ら積極的に動かしてゆかないと重たい陣形だと感じます。本書を読むと、たとえ桂損や銀損、あるいは飛車損になっても、駒をどんどん交換していって、自分に有利な局面を作ってゆく。終盤に向かって、互いに切り合うが、手番は渡さず、先に相手玉を詰ましに行く。そういう志向性を感じます。これが「さばく」ということなのでしょうか。これは居飛車であっても見習いたい感覚です。