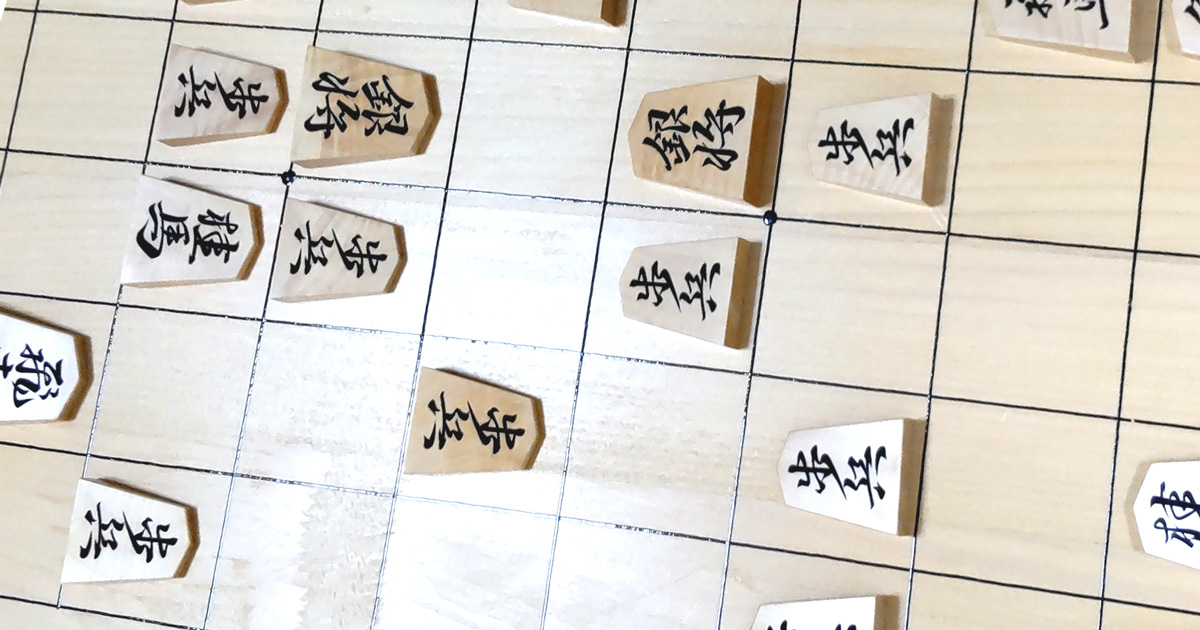穴熊という囲いを知った頃から、将棋の細い攻めとは、どういうものだろうか、とずっと考えています。守り重視で囲いに金銀4枚使ってしまったら、いったいどうやって攻めるのだろうか。飛角銀桂が各1枚使えるとしても、相手陣を突破できるのだろうか。銀の2枚目も攻めに繰り出して行った方がよいのではないか等々。
最近、攻めの棋風を強くしようと心掛けていますが、その中で、私なりに分かってきたことは、攻め駒を多数投入しても、必ずしも攻めが成功するわけではない。攻めが計画的に上手く運べば、限られた駒数でも十分である、ということです。たとえば棒銀は、細い攻めの典型と言えると思います。飛車、銀、歩の3枚だけで成り立つ戦い方です。
攻めに金銀2枚以上投入するようでは、自陣が薄くなり、逆転負けをくらう可能性が生じます。物量で押すということは、相手にも中駒や大駒が渡ります。攻めが続けば問題ありませんが、途切れたとたんに激しい反撃に会います。強力な攻めと無理攻めは紙一重です。けれど、細い攻め、限られた駒数であれば、たとえ攻めが成功しなくても、致命的な事にはなりません。その後、辛抱して戦う中で相手が何等かミスをすれば、再逆転する可能性もあります。
細い攻めは、当たり前のことですが、限られた攻め駒を駆使して戦うことです。自分自身に駒数の制限をかけて攻め筋を考えることです。すぐに敵陣突破とはならず、じりじりとしたポジション争いになります。いきなり駒得をめざすのではなく、銀が攻めにも守りにもよく働いているとか、玉側で厚みを持つとか、ちょっとしたポイントを積み重ねてゆくということです。長い手数の対局となるのも覚悟の上で、ひたすら攻めの糸口を探すことです。相手がしびれを切らして、安易な攻めを繰り出してくるならば、それがチャンスとなる時もあります。
細い攻めはまた、単発で終わってはいけません。たとえば、割打ちの銀で、飛車か金のどちらかを得ることができても、それだけであれば駒交換に過ぎません。打ち放った銀が盤上に残るか、あるいは、相手陣が乱れ、間髪おかずに次の攻めが続くことが肝要です。ずっと続く攻めだからこそ細い攻めと呼べるのであって、単発であれば、点の攻めです。
細い攻めの目標の1つは、と金を作ることです。竜や馬を作ろうとしても相手陣は最大限に警戒してきます。もちろん、それを狙えれば何よりですが、まずは、と金作りを目指すことです。と金を作るために、大量の攻め駒を投入してはいけません。それでは何も得ていません。攻め駒は基本的に不足していますが、と金が1枚できれば、金銀1枚を得たに等しいです。そして、と金を作れたということは、敵陣を突破しているということであり、その後、竜や馬を作るのも容易いことです。
細い攻めは、たとえれば、堅固なダムに小さな穴を開ける作業です。相手の守りは簡単には崩れません。力尽くで向かえば、こちらが折れてしまうときもあります。壁の弱点を探って、少しずつ堀り進め、小さな穴を開け、徐々に広げることです。細い攻めが続けば、いつかどこかで敵陣が決壊します。
【関連】