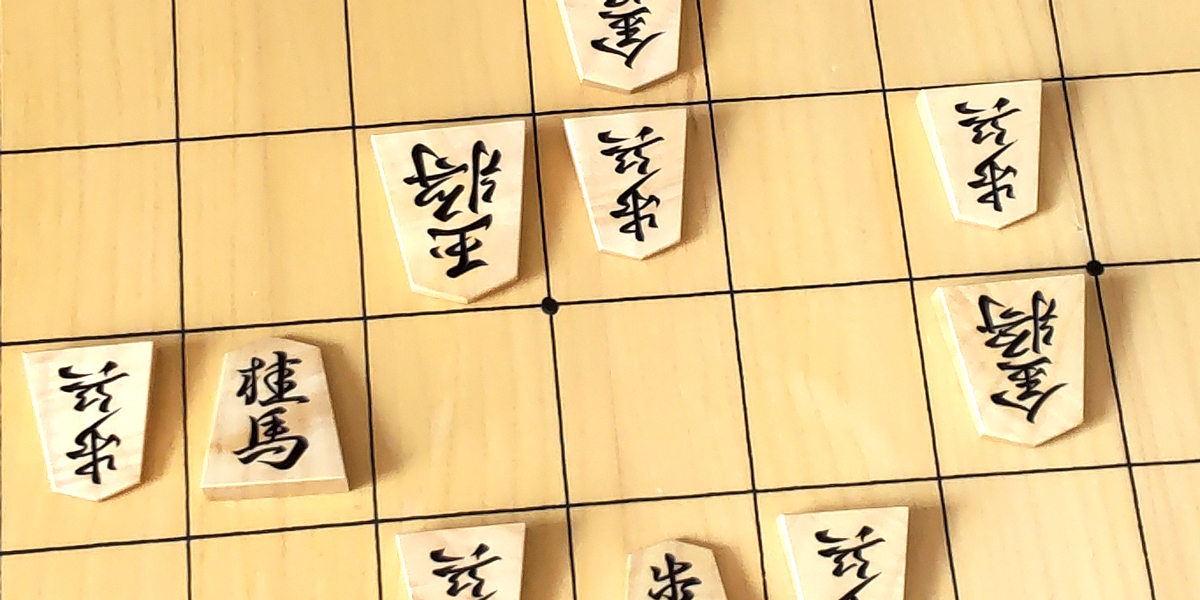将棋には「詰めろ」という用語がありますが、私は「必至」との違いがよく分からなくなってきたので調べてみました。
「詰めろ」は、まだ詰みを回避できるけれど、相手が何か受けてくれなければ、詰みがあるという局面だそうです。玉が逃げたり、守備駒を足したりして、詰みを回避することができます。逆の言い方をすると、受ける方法がある以上、まだ詰みが無い状況とも言えます。
ただ実戦では、もうかなり追いこまれており、そこから形勢を逆転するのは難しい状況がほとんどですね。もし、いったん詰みを回避しても、駒がぼろぼろと取られていって、どんどん追い詰められる状況と言えます。
相手が詰めろの状態になっていることに気づかず、直ぐに詰ませることができた、あるいは、正しい受けではなかったので即詰ませられた、といった場合もありえます。これは広い意味では「頓死」という用語が当てはまる状況に近いと思います。級位者同士の対局では時々起こることです。私もやりがちです。
それに対して、「必至(必死)」は、どんなに守備駒を足しても、あるいは玉が逃げようとしても、詰んでしまう局面だそうです。受けが無い、受けが効かない状況です。逆王手をかけ続けることでしか、詰みを先延ばしにはできません。先延ばしにしているだけなので、王手が途切れたら、詰ませられてしまいます。
逆王手をかけて必至と思われる状況が解除できるならば、それは必至でなく、詰めろだったと言えそうです。たとえば、飛車を打って、相手に王手をかけつつ、自陣の受けにも効かす、その結果、自玉の危険が回避される、といった場合です。最近の対局で、そういう事がいくつか続き、私の中で、詰めろと必至の違いがよく分からなくなってしまったようです。
詰めろは、次に王手が来る、ということになるはず。だから、詰めろは、詰めろが掛かったかどうか分かりやすく、対応策も取りやすい。
判別が難しいのは、必至の方です。必至の問題の方が、詰将棋の問題より、私にとっては格段に手強い。まだ一手必至の問題は数分考えれば分かるとしても、三手必至の問題はもうなにがなんだか見えません。実戦で三手必至をかけられたら、まったく分からないだろうなと思います。