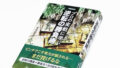振り飛車の棋書を読むと、飛車を振って戦いたくなります。
今回は、三間飛車に構えてみました。
飛車の上に、角がいる、というのは、居飛車で戦うのが基本の私にとって、違和感しかありません。
なんで飛車にフタをしちゃっているの? しかも主戦力の角じゃんか! という感覚です。角の上に飛車がいるならば、角頭を守るので、分からなくもないのですが、三間飛車の初期配置は、まずどうにも理解できません。
それでも三間飛車で戦おうとなって、いざ戦ってみます。
最初に感じていた通り、飛車先が重い。飛車がぜんぜん役に立ちません。
そうこうするうちに、相手の銀が、こちらの角頭を狙って繰り出して来たり、相手が飛車の筋を変えてきたりします。まったく何もできず、相手にいいように潰されてしまいます。
なんどか壊滅を繰り返すうちに、それでも、少しだけコツがつかめてきました。違和感しかなかった三間飛車にもメリットがあるなと思えるようにもなりました。
一つ目のメリットは、飛車の位置が、相手の角筋から逸れている、という点です。四間飛車や向い飛車ですと、ともすると相手の角の流れ弾に当たってしまうことがありますが、三間飛車ではその警戒が必要ありません。居飛車と比べても、これはメリットの1つに数えられるなと思います。
二つ目のメリットは、石田流への進展を見越して、7筋の歩(後手なら3筋の歩)を早々に伸ばせる、という点です。石田流にできれば有力な構えですが、仮に石田流にできなくても、居飛車の方は桂馬を使いづらくなります。なんとなくの感覚ですが、相手に攻めの桂馬を使わせないと、勝率で5%はアップしている気がします。
三つ目のメリットは、当初は、飛車先が重いので、どうしたって自分からは仕掛けにくい。無理攻めだけどやってみようかなと思える仕掛けさえ、ほぼ思いつきません。喧嘩っ早い棋風の人には、自然と攻めを自重する、タイミングを見るという戦型になる。そして、序盤でできる事と言えば、囲いを整えることだけ。そのうちに、相手からの仕掛けが始まる。そうなったら、その反動を利用しつつ、こちらも攻めを開始する。自玉はすっかり堅く出来上がっているので、攻めに専念できる。
四つ目のメリットは、三間飛車の飛車も、なんだかんだ位置を変えます。7筋は、相手の桂馬が守っている場合も多く、そう簡単には突破できません。相手も桂馬の警備を当てにしているので、飛車の配置換えが、相手の手薄な別の筋、予期しないタイミングだと、ずばっと飛車の直射がささる。
【関連】