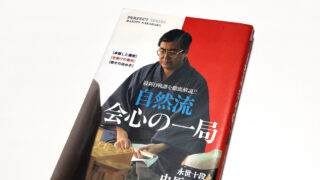 中盤
中盤 中原誠『自然流 会心の一局』
2025年9月に読了した将棋本は、中原誠『自然流 会心の一局』(日本将棋連盟、1998年)です。ここのところ名局集・勝局集を読みたい思いがあって、手に入れた一冊です。中原永世十段の自戦記8局が収録されています。中原先生と言えば、自然流。無理...
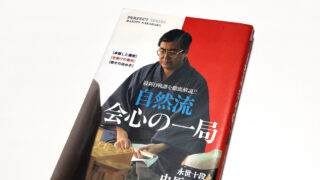 中盤
中盤  1級への技法
1級への技法  1級への技法
1級への技法 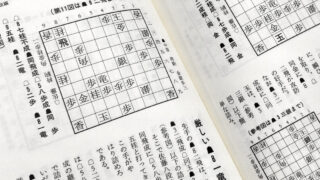 1級への技法
1級への技法  1級への技法
1級への技法  2級への技法
2級への技法 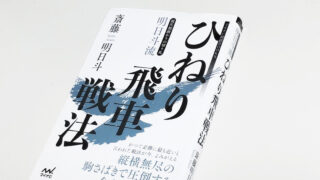 1級への技法
1級への技法  3級への技法
3級への技法 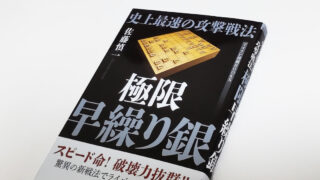 2級への技法
2級への技法  1級への技法
1級への技法