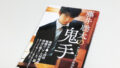最近の町道場で上手から指摘していただいたことは、角道を安易に閉ざすな、ということです。
私は居飛車で戦いますが、初手や数手目には角道を開けます。初心者の頃は、角交換に苦手意識があったので、角道を閉ざしたままとすることもありましたが、最近はまず開けます。
ところが戦いの中で、相手の銀を追い返そうと、歩を進めたところ、角筋が通らなくなりました。相手の銀は目論見通り引き下がってくれましたが、こちらは代わりに角が居座っているだけの駒になってしまいました。飛車、銀、桂馬との連携攻撃を目指していたところ、それが叶わず、中途半端な攻めになってしまいました。角道を閉ざさず、たとえ、こちらの角が相手の銀と刺し違えてでも、自分の攻めを貫くべきでした。
最序盤で駒組みを進めたり、あるいは、はじめから持久戦を目論むならば、いったん角道を閉ざすのも有り、だと思います。
ただ、私が中盤で角道を閉じてしまったのは、相手の銀を恐ろしく思い、相手の攻めを成立させないようにするだけの受けの手でした。こうなっては、角頭に弱点を抱える角行はお荷物となりかねません。角筋が通っていないということは、最低でも一手以上かけなければ、こちらから角を活かした攻撃が始まらないことを意味します。一段階、守勢に入ってしまったということです。
飛車に匹敵する攻撃力を活かさないのはもったいない。角道を閉ざしては相手にとって何も脅威にならない。角は睨むだけ局面に影響を与えられる。中盤以降、一手も引いてはならない局面ではなおさらだ。そういう教えをいただきました。
【関連】