 3級への技法
3級への技法 時間が無くても、互いの手を読む
将棋の終盤で熱くなってくると、視野が狭くなりがちだと思います。特に、自分の方の攻めの手は幾通りも数手先もしっかり読むのに、相手の方の指し手はじっくり見ない。それがために逆転をくらってしまうケースはあるように思います。相手の指し手を読むという...
 3級への技法
3級への技法 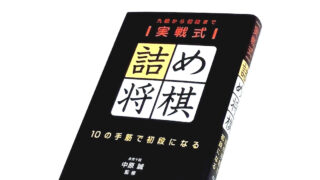 3級への技法
3級への技法 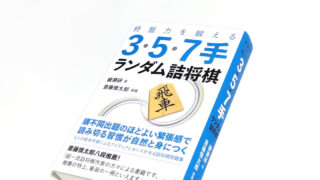 3級への技法
3級への技法  3級への技法
3級への技法  3級への技法
3級への技法  2級への技法
2級への技法  2級への技法
2級への技法 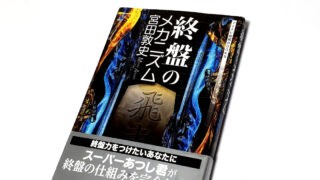 3級への技法
3級への技法  13級への技法
13級への技法  2級への技法
2級への技法